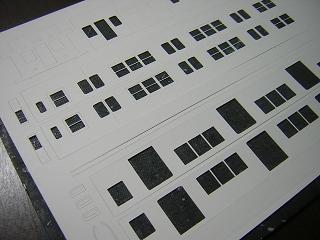 |
窓抜き作業
・作業開始。
カッティングマシンでつけてもらった溝をカッターでなぞり、窓、
ドアなどを切り抜いていきます。
一気に切り込みを入れず、徐々に力を入れてなぞっていくのが
良いかと思います。 |
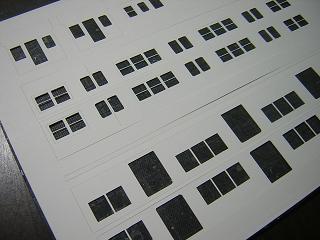 |
窓抜き作業
・中間車完了。
|
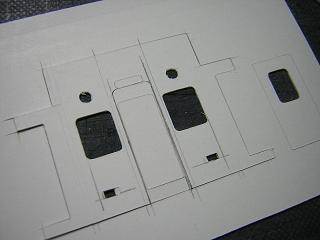 |
前面考察
・貫通ドア部は7001-7101形と同様の構成とするため、貫通ドア部を
ごっそり切り抜くこととし、切り取り部をケガいておきます。
またテールライト位置も若干移動しています。
★ここでの失敗→貫通ドア部切抜きを広げるのを忘れていました。
結果、貫通ドアが狭いままで完成としています。 |
 |
前面考察
・前面をコの字型に曲げて行きます。
この段階では強度的にも弱いので取り扱い注意です。 |
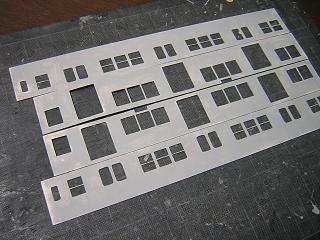 |
下地処理
・強度確保も兼ねて、サーフェイサーを表裏筆塗りした後、400番の
ペーパーで軽く表面研磨しています。
平滑処理を行った後、均一になるよう再度サーフェーサーを
スプレーで吹付けています。
このときはGSIクレオスのMr.サーフェイサー500を使用して
います。
写真は先頭車7801形。 |
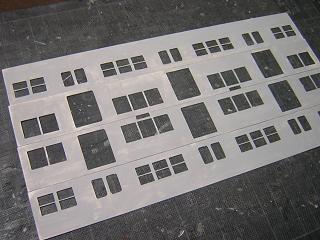 |
下地処理
・中間車7901形も同様です。 |
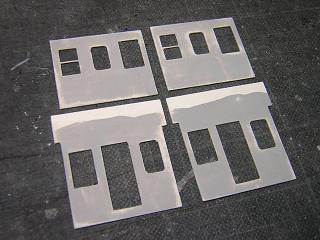 |
下地処理
・7901形用妻面。 |
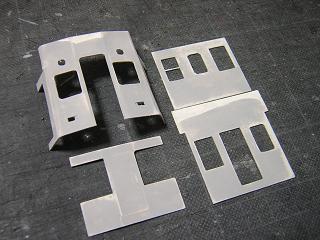 |
下地処理
・7801形用前面と妻面。 |
 |
下地処理
・一旦平滑処理を行った後、均一になるよう再度サーフェーサーを
スプレーで吹付けています。
このときはGSIクレオスのMr.サーフェイサー500を使用しています。
写真は7801形。 |
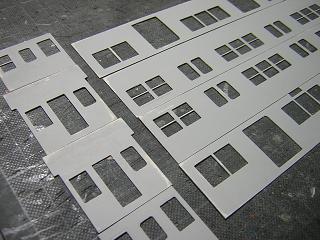 |
下地処理
・中間車の7901形も同様です。 |
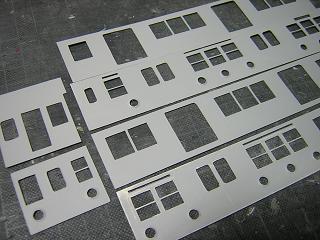 |
側板製作
・裏板には表板、裏板接着時にサーフェーサーを流込めるよう
ポンチで○穴を開けています。 |
 |
側板製作
・表板と裏板の接着。
目玉クリップで固定し1昼夜程度寝かして起きます。 |
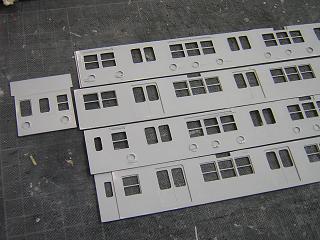 |
側板製作
・側板の完成。
妻板も同様に製作しています。
2012-4/8 |
 |
側板補強材取付け
・補強と、裾部R表現を兼ねて、側面補強材を接着します。
今回2mm×2mmの角材を用いています。 |
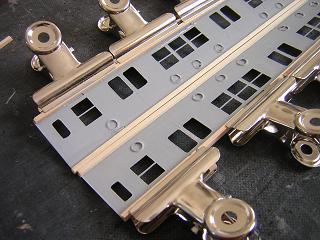 |
側板補強材取付け
・側面の寸法に角材を切り出し、木工用ボンドで接着します。
乾燥に時間がかかるため、2両/日程度の作業となります。
なお71005F製作時に客用窓レイアウトが若干低めに感じた為、
今回裾部の補強材を0.5mmずらして接着しています。
|
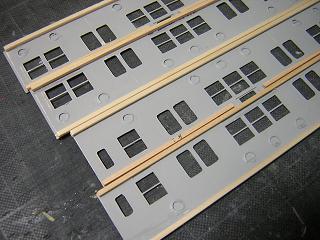 |
側板補強材取付け
・補強材取付け完了。 |
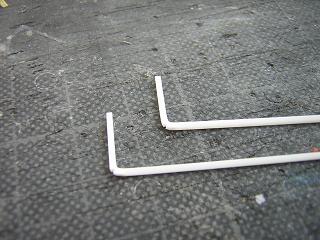 |
前面貫通ドア周辺処理
・貫通ドア部の窪みを表現する為、貫通ドア枠を1mm角のプラ角材を
用いて表現してみます。 |
 |
前面貫通ドア周辺処理
・ドア枠として、1mmのプラ角材を貼り付けています。 |
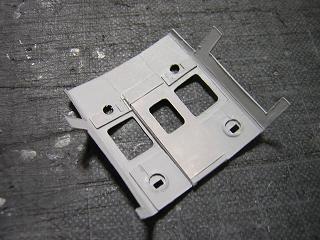 |
前面貫通ドア周辺処理
・貫通ドアを接着。
同時に貫通ドアの上部と下部の隙間にも型紙の余分な箇所から
適当なサイズに切り出して貼りつけています。 |
 |
方向幕検討製作
・実車では方向幕は屋根肩のR部に出っ張った形で取付いて
いますので、型紙では別パーツ化されています。
ただ、若干抜き穴サイズが小さいようでしたので、自分で
開けなおしてみました。
前面は写真のようになります。
ただ、方向幕部の接着は、屋根を取り付けた後に行います。 |
 |
車体箱組
・まずは側板と妻板を接着します。
プラキットと同様に、まずL型に組んで、それを組合わせる手順で
行っています。
接着は木工用ボンドを使用しています。
|
 |
車体箱組
・前面側も同様です。 |
 |
車体箱組
・7835と7935。共に箱状になりました。
このあと補強処理を施していきます。 |
 |
車体補強
・車体補強として、天井部と床部に角材を入れます。
2mm厚の角材を切り出して使用します。 |
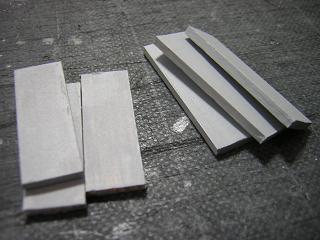 |
車体補強
・切り出した補強材は、表面処理としてサーフェイサーを筆塗り
しています。 |
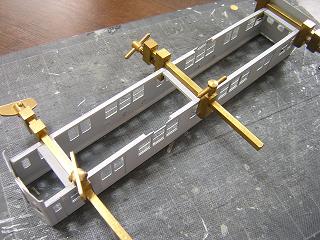 |
車体補強
・補強材は、天井部は両端と真ん中の3箇所に入れています。
ゴム系接着剤を用いて、ハタガネで固定して1昼夜寝かせて
います。 |
 |
車体補強
・補強材の取付け完了。
床部の補強材は床板固定用ネジを設けるため、Φ2.0mmの穴を
開けておき、M2×6mmネジとナットで固定しています。
2011-4/15 |
 |
屋根板検討
・7801-7901形2次車は、新造時ラインデリア装備車として、かなり
平坦な屋根R形状となっています。
各種写真や、屋根の高い7001-7101形と並べて大体のR形状を
決めていきます。 |
 |
屋根板製作
・ざっくりとR形状をケガいてみました。
平坦にしたつもりですが、これでも結構Rが付いているように
見えます。 |
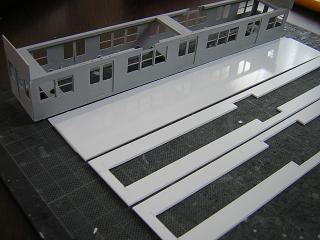 |
屋根板製作
・今回も、屋根板にはプラ板を使用しました。
型紙の図よりt=1.2mmのプラ板(確か)計3枚を重ねます。
室内側の2枚は、KATO製室内灯ユニットを組込む為、導光材
部分をくり抜きます。 |
 |
屋根板製作
・こちらは先頭車用。
ヘッドライト/方向幕とのあたり部をくり抜いています。 |
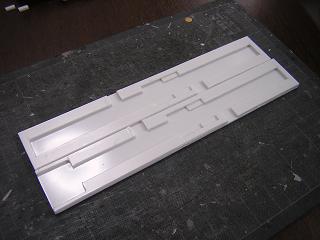 |
屋根板製作
・3枚のプラ板を張り合わせた状態。 |
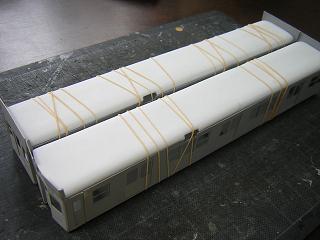 |
車体仮組立
・車体と屋根板を接着します。
プラと木の組合せの為、ゴム系接着剤を使用しました。
接着後、固定するまで1昼夜寝かしています。 |
 |
車体組立
・車体と屋根板が組み合わさりましたので、接合部をパテで
平滑化します。 |
 |
車体組立
・7001-7101形では幕板部が目立ちましたので、0.5mm位置を
ずらしました。
補強材の隙間にもパテを埋めています。 |
 |
車体組立
・前面も屋根Rなどを削りだしていきます。 |
 |
車体組立
・前面も同様にRをつけていきます。 |
 |
車体下地処理1
・側面含め平滑処理を行って、サーフェイサー500を吹きつけた
状態。 |
 |
車体組立2
・前面方向幕部の表現を試みます。
まずは前面部を貼り付け、後から上側に0.3mmケント紙を
貼り合わせます。 |
 |
車体組立2
・上側はこのように貼り付けています。 |
 |
車体組立2
・側面方向幕部も同様に0.3mmのケント紙を用いて行います。 |
 |
車体組立2
・側面方向幕を車体内側から。 |
 |
車体組立2
・方向幕横の隙間は上側と同様に0.3mmケント紙を貼り付けて
います。
(写真では右側に相当) |
 |
車体組立2
・側面方向幕の左右上側にケント紙を貼り合わせて、隙間を
パテ埋めした状態。
|
 |
車体組立2
・前面方向幕も同様に処理しています。
2012-4/22
|
 |
雨樋取付け
・車体にテープで仮止めした後に、順に薄めたサーフェイサーを流し、車体に
固定していきます。 |
 |
雨樋取付け
・前面部アップ。 |
 |
雨樋取付け
・側面方向幕部アップ。 |
 |
雨樋取付け
・雨樋の取付け完了。 |
 |
雨樋の取付け
・妻面の雨樋も同様に取付けます。 |
 |
車体下地処理2
・雨樋を含めて下地処理を行います。
GSIクレオスのMr.サーフェイサー500を吹付けています。 |
 |
靴ヅリ取付け
・型紙から適当な幅に切り出し、車体に貼り付けていきます。
手法は雨樋と同様です。 |
 |
前面ライト加工
・ヘッドライト台座の再現方法も7101/7828と同様です。
ライトリムにはTABASA PN-028の250WヘッドライトA
(外径Φ2.3mm)を使用するため、一回り大きいΦ3.5mmのケント紙
を貼付け、瞬間接着剤で固めた後にΦ2.7mmで穴を開けなおします。 |
 |
前面ライト加工
・ヘッドライト台座を貼り付けた状態。
ちなみに写真は誤ってΦ4mmを貼り付けた状態。
(塗装後に気づいて修正しています)
|
 |
前面ライト加工
・Φ2.7mmで穴を開けた状態。 |
 |
車体下地処理3
・仕上げの下地処理を行います。
GSIクレオスのMr.サーフェイサー1000を吹付けています。 |
 |
車体下地処理3
・しかし、こちらも肩のRを削りすぎたのか、7801型3次車というより
3801型のように 見えて仕方がありあません...。 |
 |
屋根上機器取付け準備
・パンタ周辺配管やクーラー実装に向けて、実装位置をケガいて
いきます。
写真は7835のパンタ周辺。 |
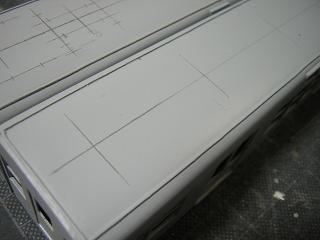 |
屋根上機器取付け準備
・こちらは7935のクーラー取付け位置。 |
 |
7835屋根上機器取付け準備
・とりあえずパンタ取付穴を開けます。
パンタグラフはフクシマのPT48を使用します。
Φ1.0mmで取付穴を開けておき、Φ1.3mmでタップを切って
おきます。
素材がプラなので、ねじ山を潰さない様に慎重に作業を
行います。 |
 |
7835屋根上機器取付け準備
・パンタ台座を瞬間接着剤で接着します。
パーツはエコーNo.614 パンタ碍子台を使用しています。
2012-4/29
|
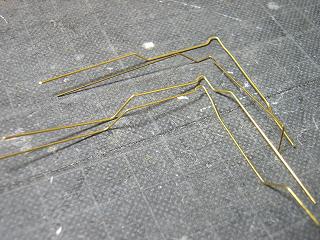 |
屋根上配管の製作1
・各種高圧配管関係。
高圧配管系にはΦ0.6mm、Φ0.5mm、空気作用管にΦ0.4mmの
真鍮線を使用しています。
なおパンタ台に接続される箇所は、一部真鍮パイプを使用して
います。 |
 |
屋根上配管の製作1
・梅田寄りパンタグラフ周辺を山側から。 |
 |
屋根上配管の製作1
・梅田寄りパンタグラフ周辺を海側から。 |
 |
屋根上配管の製作1
・神戸側妻面レイアウト。
実車は既に引退していることから、比較的近い7861-7961型の
配管を参考にしています。
|
 |
妻面ステップ取付
・妻面のステップには、マッハのステップを使用しています。
また一番上の手摺はΦ0.3mm真鍮線を使用しています。
なお接着には瞬間接着剤を使用しています。 |
 |
前面ステップ取付
妻面同様、1番上の手摺はΦ0.3mmの真鍮線です。
屋根上の手摺も同様です。 |
 |
前面ステップ取付2
1番上の手摺はΦ0.3mmの真鍮線を用いて表現しています。 |
 |
妻面ステップの取付2
・7835のパンタ側妻面も同様です。 |
 |
妻面ステップの取付2
・7935の妻面も同様です。 |
 |
クーラー台座製作
・クーラーの台座として、t=2.0mmのプラ板を切り出していきます。 |
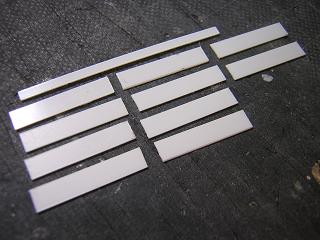 |
ラインデリアカバー製作
・ラインデリアカバーもt=0.5mmのプラ板を切り出しています。
7001と同じ幅にしています。 |
 |
クーラー台座とラインデリアカバー実装
・屋根クーラー台座とラインデリアカバーを接着します。 |
 |
クーラー台座とラインデリアカバー実装
・7835パンタグラフ周辺の図。山側より。 |
 |
クーラー台座とラインデリアカバー実装
・7835パンタグラフ周辺の図。海側より。 |
 |
テールライトケース製作
・角型のテールライトケース。7105F、7828F同様にエコーの札差を
使用することにしました。
車体と同じケント紙に札差を接着して表現します。
|
 |
テールライトケース接着
・車体に接着。
接着には瞬間接着剤を使用しています。 |
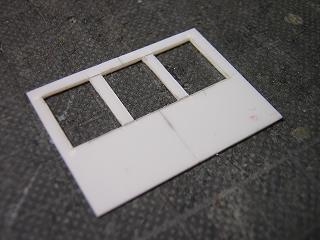 |
運転台仕切りの製作
・t=0.5mmプラ板を切り出しています。 |
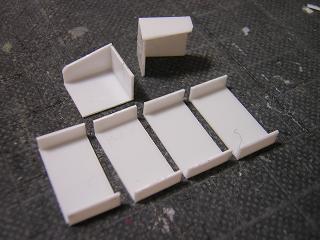 |
ライトケースの製作
・各種ライト類点灯化を図る為、ライトケースを製作します。
写真は標識/尾灯用と側面方向幕用。
t=0.5mmのプラ板から作成しています。 |
 |
前照灯用ライトケースの製作
・t=0.5mmプラ板から、ライトケースを製作します。 |
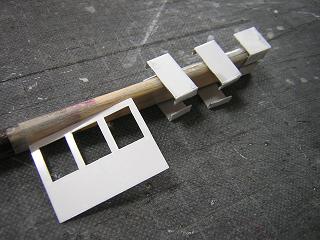 |
運転台仕切りとライトケースの塗装準備
・ライトケースは下地に銀を塗装後、室内色を塗装します。
2012-5/6 |
 |
室内塗装1
・塗装フェーズに入ります。
まずは室内壁から。
準備として車体外側をマスキングします。 |
 |
室内塗装1
・まずは壁の薄緑から。
マッハカラーNo.218:淡緑1号をGSIクレオスの薄め液で薄めて
使用しています。 |
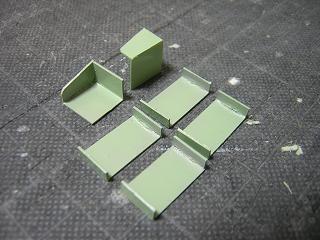 |
ライトケースの製作・塗装
・標識/尾灯用と側面方向幕用。素材はt=0.5mmプラ板を使用して
います。
車体と同時に塗装です。 |
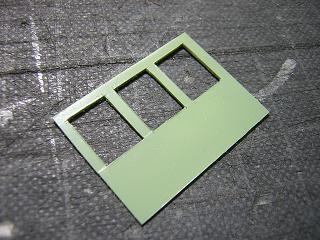 |
運転台仕切りの製作・塗装
・こちらもt=0.5mmプラ板を淡緑1号で塗装しています。 |
 |
室内塗装2
・次は天井。
壁面をマスキングした後に、GM37:白3号を吹いています。 |
 |
車体塗装1
・まずはクリームを塗装。
マッハNo.52:阪神クリームを使用します。 |
 |
車体塗装1
・マスキングを行い、車体下部に赤を吹きます。
塗料は同じくマッハNo.53:阪神赤を使用しています。 |
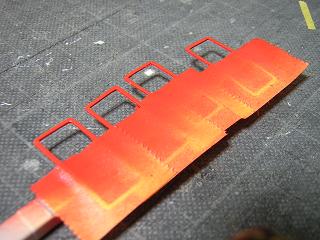 |
車体塗装1
・同様に貫通路幌枠、ステップ、車外スピーカーなども塗装して
おきます。 |
 |
車体塗装1
・車体のマスキングを剥がした状態。 |
 |
車体塗装1
・マスキングを剥がした状態。写真は貫通路幌枠と踏み板。 |
 |
車体塗装2
・塗料の吹き込みは、リワークを施しておきます。 |
 |
車体塗装2
・前面も同様、塗料の吹き込みは、リワークを施しておきます。 |
 |
車体塗装3
・貫通路ドアは車内と同じ淡緑を吹いています。 |
 |
車体塗装3
・車体のマスキングを剥がした状態。 |
 |
屋根上配管の製作2
・パンタ台に接続される箇所は、Φ0.6mmの真鍮パイプを使用し、
中にΦ0.3mmの真鍮線を通しています。 |
 |
屋根上配管の製作2
・真鍮線を通した真鍮パイプを実装します。
固定は瞬間接着剤を用いています。 |
 |
屋根上塗装
・屋根塗装に備えマスキング。 |
 |
屋根上塗装
・GSIクレオスのB-504:メタルプライマーを吹いた後、GM9:
ねずみ1号を吹いています。 |
 |
屋根上塗装
・マスキングを剥がした状態。
これから細部色入れなどを行っていきます。 |
 |
各種パーツ塗装
・クーラーはKATO12系客車用を使用。
GM14:灰色9号を使用します。 |
 |
各種パーツ塗装
・屋根上ランボードやヒューズボックスはプラ板で作成。 |
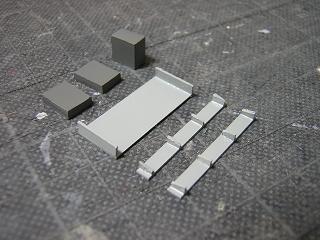 |
各種パーツ塗装
・ランボードは、ヒューズ台とランボードは色のニュアンスを変えて
みました。
GM9:ねずみ1号と、GM14:灰色9号を調合しています。
ヒューズボックス類はGM35:ダークグレーで塗装します。 |
 |
床板塗装
・室内側はGM14:灰色9号を、床下側はGM9:ねずみ1号を吹付けて
います。 |
 |
窓Hゴム表現
・前面窓と表示幕廻りに色差しを行います。
塗料はGM9:ねずみ1号を使用しています。 |
 |
窓サッシ、Hゴム表現
・窓サッシには銀色を、表示幕廻りにグレーの色差しを行います。 |
 |
運転台製作
・運転台に色指ししておきます。 |
 |
座席塗装
・室内シートはカツミ製プラロングシートを用いています。
寸法に併せて切り出しています。 |
 |
座席塗装
・塗装は水性カラーのワインレッドを使用しています。
2012-5/20。 |
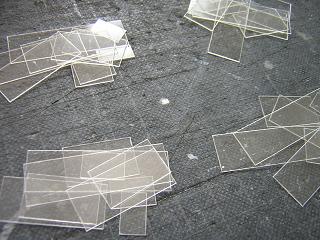 |
窓ガラスの製作
・t=0.2mmのプラ板を窓サイズに切り出しています。 |
 |
窓ガラスの貼付け
・各窓、方向幕に車体裏側から貼り付けていきます。
写真は前面乗務員窓と方向幕部に貼付けた図。 |
 |
窓ガラスの貼付け
・側面も同様です。 |
 |
サボ掛け製作
・サボ掛けは7105F/7828F製作時の余剰パーツを用いています。 |
 |
前面パーツ取付
・標識掛けやワイパー類を実装します。 |
 |
前面幌の製作
・阪急8000系付属の幌をレジンコピーし、車体にあわせ上下左右
方向に若干寸法を詰めておきます。
こちらのパーツも7105F/7828F製作時に余分に作っていました。 |
 |
各種パーツ塗装
・パンタグラフはフクシマPT48を使用。
流通よりグレーしか入手できなかったので銀に塗装します。
併せてライトリムも銀に塗装しています。
前面幌は、正面のみ銀塗装し、側面の蛇腹部はグレー塗装と
します。 |
 |
各種パーツ塗装
・台車のスペーサーはt=0.5mmのプラ板を2枚重ねたものを使用。
前面幌の側面と併せて、GM9:ねずみ1号を吹いています。 |
 |
標識灯用レンズの製作
・標識等のレンズも7105F/7828F同様、とある装置のLEDレンズを
取り出し、周囲を削って適当な大きさにしました。 |
 |
標識灯用レンズの製作
・標識灯レンズを実装。
レンズ面の仕上がりがイマイチですが...。 |
 |
看板類実装
・阪神特急のシンボルでもある特急看板を実装します。
7105F/7828F製作時の残品で、クワ工房NO-E12:先頭列車行先板
(阪神電鉄A)をカラーコピー(縮尺95%)したものをt=0.2mm透明プラ板
に貼付けています。 |
 |
方向幕製作
・方向幕は、クワ工房のNo-D42:前面側面列車行先(阪神8000系
他特急)をカラーコピー(95%縮小)した後、透明プラ板に貼付けて
います。 |
 |
方向幕実装
・先に作成した方向幕を車体裏側から貼り付けます。 |
 |
方向幕実装
・前面も同様です。 |
 |
方向幕実装
・全体のイメージです。
この時点で貫通路を広げるのを忘れていることに気づきましたが、
あとの祭り...。
まぁ雰囲気でということで進めます。
>既に阪神7835というより3801の様な顔になっていますが...。 |
 |
台車加工
・阪神7001形-7101形では台車にFS-341を使用していますが、
残念ながら市販品は存在しません。
よって台車枠が比較的似ているTR-55を使用しました。
メーカーは日光製を使用します。 |
 |
台車加工
・TR-55そのままだとブレーキシューが両抱き方式のため、外側の
ブレーキシューを切り取ります。 |
 |
台車加工
・ブレーキシリンダーは、山陽電鉄3050系3058F用にDT32から
KW-15を製作した際、余剰となったパーツを捻出します。
数が足りないのでキャストコピーしています。 |
 |
台車の塗装
・台車はマッハのNo.234:灰色1号を吹付けています。 |
 |
前面ヘッドライト台座の修正
・車体を眺めていると、どうもヘッドライト周辺に違和感を覚え、
7105Fの車体と製作記をじっくり確認すると、台座の寸法は
Φ4mmでは無くΦ3.5mmであることが解りました。
ということで、台座を一旦剥がしてΦ3.5mmで作り直します。 |
 |
前面ヘッドライト台座の修正
・台座をΦ3.5mmに修正しライトリム挿入用のΦ2.7mm穴を
開けた状態。
この後、前面の塗装リワークに入ります。 |
 |
前面ヘッドライト台座の修正
・塗装リワーク完了。窓周りのHゴム色指しなども行って
おきます。 |
 |
前面ヘッドライト台座の修正
・再度各パーツを取り付けた状態。
これで良しとしますが、何か似てない感じです。
意外と阪神の顔は難しいです。
2012-5/27 |
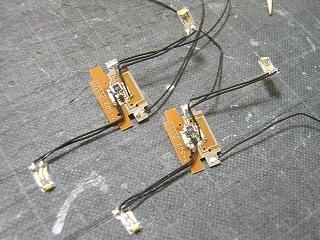 |
室内灯ユニット加工
・今回も室内灯にはKATO製のライトユニットを使用していますが、
側面方向幕点灯用の電流も、当ユニットから供給します。
そのため、電流値を確保するにあたり、抵抗を680Ωから470Ωに
変更しました。
>ライトユニットに実装されているブリッジダイオード。型名は
分かりませんが、パッケージが小さいことから順方向電流も
大きく取れないと思われ、これ以上抵抗値を小さくするのは
危険かと思います。
いずれにせよ、当方の値は参考程度にしてくださいませ。
(焼損等の責任は負えませんので)
側面方向幕用のLED配線はKATOのライトユニットに実装された
LEDの両端と半田付けしています。 |
 |
標識/尾灯の配線
・標識/尾灯ユニット製作します。
ヘッドライトユニットとの接点にシール基板を用いています。
その他配線は7105F/7828Fと同様です。 |
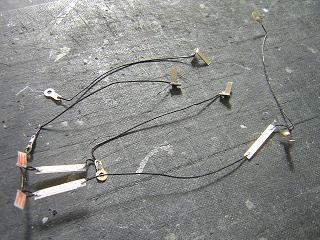 |
標識/尾灯の配線
・車輌の配線全体の図。
上が7935用、下が7835用です。 |
 |
前照灯用ライトユニットの製作
・先に製作した前照灯と前面方向幕ライトを半田付けします。 |
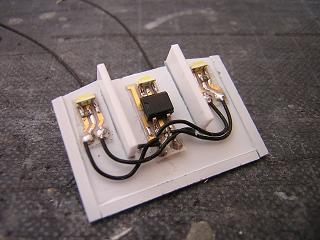 |
前照灯用ライトユニットの製作
・前面ライト一式をライトケースに接着します。
と、まぁ2011年末までに、ここまで作業が進んだので、正月
休みの工事で年明けの運転会に間に合う算段でしたが、年末から
急遽入院となり、作業中断となりました。 |
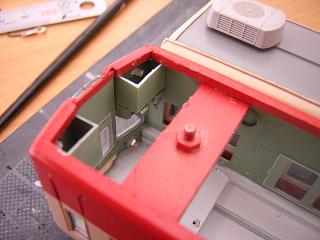 |
標識/尾灯用ライトケース実装
・先に塗装まで済ませたライトケースと運転台を実装します。 |
 |
ライトユニット類の実装
・室内灯用のライトユニットを車体に組み込みます。
あらかじめKATOの室内灯セット付属の反射テープを貼付け、
ライトユニットを車体中央部に配置します。 |
 |
ライトユニット類の実装
・ライトユニット実装後、方向幕のライトケースを実装します。 |
 |
座席実装
・塗装が完了した座席を室内に組込みます。
写真は車体中央部。 |
 |
座席実装
・上と同じですが、運転台〜車体中央部にかけての図。 |
 |
前照灯用ライトユニットの実装
・先に製作した前面ライト一式の終電用配線を現物にあわせます。
集電はシール基板を使用してみます。
|
 |
前照灯用ライトユニットの実装
・運転室仕切りを入れ、集電用端子を車体に接着して各種ライト
ユニットと運転台の実装は完了です。
|
 |
前照灯用ライトユニットの実装
・前面側から見た図。。
|
 |
台車実装
・台車スペーサーにΦ2.0mmのネジ用穴を開けておきます。
|
 |
台車実装
・組立の終わった台車を車体に実装し、室内灯関係の配線を
行います。 |
 |
台車実装
・配線は写真のようにしています。 |
 |
屋根上配管の製作2
・パンタからヒューズボックス周辺の配管を作成します。
Φ0.3mmの真鍮線を用いています。
|
 |
屋根上配管の製作2
・作成したΦ0.3mmの配管を主配管?に瞬間接着剤で接着
します。
これにより主配管からケーブルが出ている感じを再現した
つもりです。 |
 |
屋根上配管の製作2
・パンタ周辺を神戸寄り妻面からの俯瞰。
|
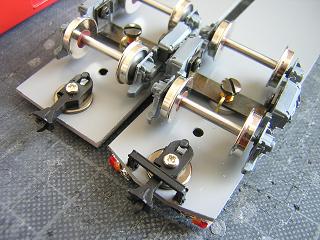 |
連結器の実装
・他編成との連結面はバンドーン型連結器もどきとして密着
連結器を実装しています。 |
 |
連結器の実装
・7835-7935間の連結面はACEカプラを使用しました。 |
 |
連結器の実装
・密着連結器は追随性を高める為、スプリングを挿入し、連結器が
真直ぐになるようにしています。 |
 |
車側灯の実装
・パーツはTOMIXの455系用を使用しています。 |
 |
無線アンテナの実装
・アンテナはプラ引き伸ばし棒とプラ板から自作しています。 |
 |
車番の作成
・車番はマッハ製の阪神社紋・数字(エッチングパーツ)を使用
しています。
車体貼付け前に切り抜いた番号を白塗装しておきます。 |
 |
床下機器の製作
・7105F/7828Fで製作した床下機器をキャストコピーで再製作
します。 |
 |
床下機器の実装
・機器レイアウトはバイブルであるレイルロード社の”サイドビュー
阪神”と先に製作した7828Fを参考に、それらしい機器を並べて
います。 |
 |
車番貼付け
・先に塗装した車番を一文字ずつ貼付けていきます。
写真は7935側面車番。 |
 |
車番貼付け
・7835も同様です。 |
 |
車番貼付け
・7835の前面も小さいサイズの番号を貼付けます。 |
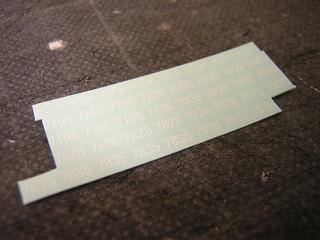 |
社紋、妻面車番インレタ作成
・7105F/7828F製作時にデカールを作成していましたが、この時に
7835Fの番号も入れていましたので、これを使います。 |
 |
社紋デカール貼付け
・車体側面に社紋を貼付けます。 |
 |
妻面車番デカール貼付け
・車体妻面に車番を貼付けます。 |
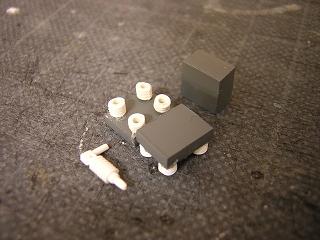 |
ヒューズボックス製作
・先に製作・塗装したヒューズボックスに、半分に切った485系の
碍子を接着した表現しています。
かなりオーバースケールですが、雰囲気ということで。 |
 |
ヒューズボックス類の実装
・先に実装したヒューズ台にヒューズボックス、パンタ横ランボード
などを接着します。
山側より俯瞰。 |
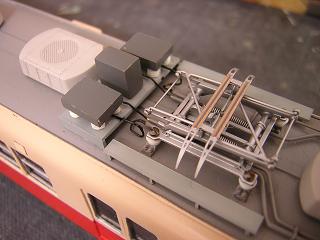 |
ヒューズボックス類の実装
・配管ルートは現在の7861形を参考にしていますが、当時は
棒ヒューズを使用していたと思われ,若干配管ルートが違って
いる可能性があります。
まぁ雰囲気ということで...。 |
 |
ヒューズボックス類の実装
・パンタグラフ周辺を山側梅田寄りから俯瞰。 |
 |
落成
・途中入院による中断がありましたが、これにてひとまず落成〜。 |
 |
7935(左)と7835(右)
・ヘッドライト点灯の状態。 |
 |
7835を側面から
・側面方向幕点灯状態。
今回勘違いして制限抵抗(1kΩ)を外してしまいました。
これにより室内灯がかなり暗くなってしまったのではないかと
思われます。
どこかで手直し予定です。
(室内灯システム自体を根本的に見直すかもしれませんが)
2012-6/3 |
今回の直材費
★真鍮線材や配管止め、ステップは共通部品として当該金額に含めず。
★各パーツ類は購入時の価格(購入店により税込、税別混在)で記載。以降価格が変わっているもの多数あります。
・イチフジモデル阪神7801/7901-2次型紙(カット済)×2:@\1,260×2=\2,520
・フクシマ PT48グレー×1:@\3,360×1=\3,360
・フクシマ#1105 碍子(直流)×0.5:@\315×0.5=\158
・フクシマ#5010 1.2×8ネジ×0.4:@\315×0.4=\126
・エコーNo.614 パンタ碍子台×0.5:@\200×0.5=\100
・エコーNo.1607 貫通渡り板×0.25:@\250×0.25=\63
・エコーNo.2633 電車用胴受(新型用A)×0.25:@\420×0.25=\105
・エコーNo.1690 私鉄電車用運転台(一般型)×0.5:@420×0.5=210
・エコーNo.PW-2647-25 精密ワッシャ×0.25:@\100×0.25=\25
・エコーNo.B-2000 精密ナット(M2用)×0.25:@\100×0.25=\25
・エコーNo.2649 ジャンパ栓受(車体用E)×0.5:@\420×0.5=\210
・精密ビス(M2×6)×0.25:@\105×0.25=\26
・エンドウ#5702 密着連結器×1:@\1,575×0.2=\315
・エンドウ#2704 ワイパーA×1:@\315×0.125=39
・エンドウ#5802 ジャンパー連結気受(電車用-床下側-2連A):@\294×1=\294
・日光モデル TR-55×2:@\1,785×2=\3,570
・日光モデル 木製床板用センターピン×2:@273×2=546
・カツミ ACEカプラー×1:@\378×1=\378
・カツミ プラロングシート×2:@\315×2=\630
・KATO#7-503 (HO)白色室内灯セット×2:@\1,092×2=\2,184
・TAVASA#PN-028 250WヘッドライトA×1:@\250×1=\250
・マッハNo.52 阪神クリーム×1:@\550×0.25=\138
・マッハNo.53 阪神赤×1:@\550×0.25=\138
・マッハ阪神社紋・車番:@980×0.25=¥245
・白色LED:@\30×11=330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
合計:¥15,984 → ¥7,992/両の最安値となりました。
2012-6/10
|