 |
・妻板ステップ穴あけ(2024/8/24)
まずは妻面ステップ穴開け。
マッハさんの差し込みステップを使用しますので、Φ0.5mmの
穴をあけておきます。 |
 |
・妻板ステップ穴あけ(2024/8/24)
Mc、M車の大阪寄り妻板には空気配管用(と思われる)
がありますが、製品では省略されているため、配管止め
用の穴を開口しておきます。 |
 |
・前面ライトケース取付(2024/8/25)
前面に取付けるパーツ類は箱組の前に半田付け
しておきます。
写真はライトケースとキャブインテリア支えパーツを
半田付けした状態。
まずは重い腰を上げたということで...。
2024/9/15 |
 |
・乗務員ドア取付(2024/8/25)
乗務員ドアと手摺を先に取り付けておきます。 |
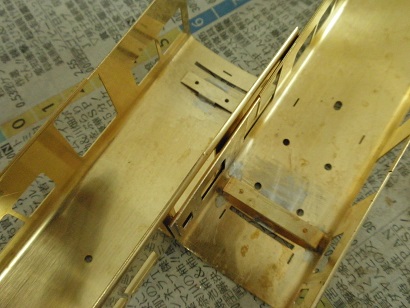 |
・屋根裏パーツ類の取付(2024/8/25)
屋根裏に貼り付ける、仕切支えなどのパーツも
はんだ付けしておきます。 |
 |
・車体アングル取付(2024/8/25)
アングルも箱組前に取付けておきます。 |
 |
・車体アングル取付(2024/8/25)
ドア下靴ヅリをガイドにする構成ですが、当たりが
弱い為、写真の様な工具ではさんで固定して半田を
流します。 |
 |
・車体アングル取付(2024/8/25)
ドア下靴ヅリ部のアップ。
もう少し出っ張って欲しい気がします。 |
 |
・車体アングル取付(2024/8/25)
半田付け完了。
キサゲで余分なはんだを削り落とします。 |
 |
・車体アングル取付(2024/8/25)
6両アングル取付完了。
そのあと、妻板と前面を半田付けして箱組します。 |
 |
・車体箱組(2024/8/25)
6両箱組完了。
|
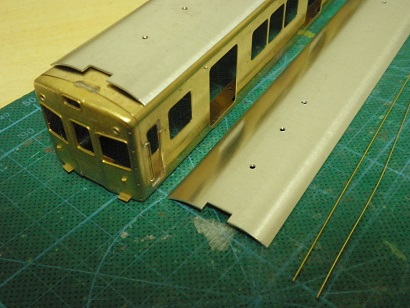 |
・雨樋取付(2024/8/30)
雨樋を取付けます。
位置決めにはアルミ製の位置決め治具が添付されている
ので活用します。
雨樋用はΦ0.5mm真鍮線が同封されていますが、過去製作
した車両に合わせ、0.6×0.3mmの帯材に変更しています。
|
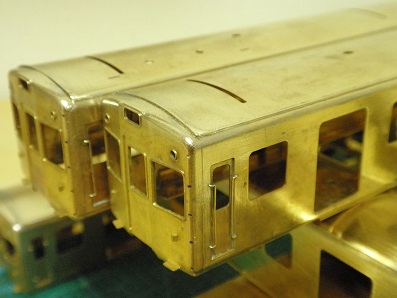 |
・雨樋取付(2024/9/1)
雨樋取付完了。
先頭車前方のコーナーパーツも合わせて
取付けます。 |
 |
・雨樋取付(2024/9/1)
6両雨樋取付完了。 |
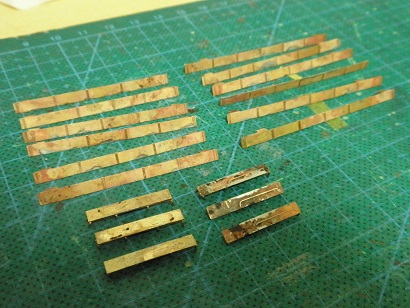 |
・ランボード組立(2024/9/1)
ランボード類は説明書に従い、ランボード板部と
台座部分を半田付けします。
足部分が細く、強度が無い為、足俺に注意が必要です。
|
 |
・モニタルーフ組立(2024/9/1)
モニタルーフ用妻板を半田付けします。 |
 |
・モニタルーフ組立(2024/9/1)
車体に乗せて見たくなるので、乗せてみました。 |
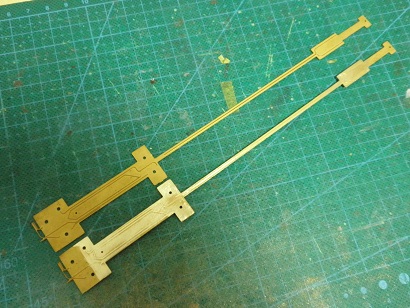 |
・配管渡り板組立(2024/9/4)
配管渡り板ですが、パーツはエッチング成型で、
主配管もモールドで表現されています。
数十万する金属製品の表現レベルがモールドで
良いのか?と悩むこと数日。
思い切って配管やり直すこととして、モールド表現を
削り落とすことにしました。
もう後戻りできません。
2024/9/22 |
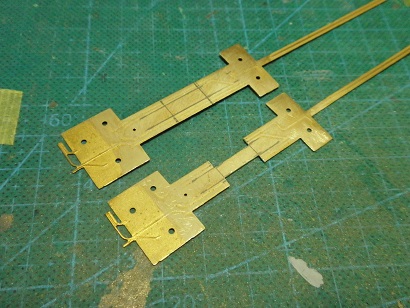 |
・配管渡り板組立(2024/9/6)
加えてレイルロード社の2000系vol.1を見ていると、
昇圧後には渡り板形状が変わっているようです。
(知らなかった...)
ということで、切り込みを入れました。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/6)
Tp車6692用のパンタ台を入手出来たので、早速車体に
実装。
クーラー位置もM車と同じ位置に変更します。 |
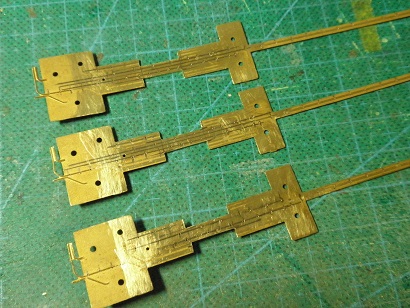 |
・配管渡り板組立(2024/9/10)
配管ルートをケガキ、配管止め位置を決めます。
その後配管止め位置をΦ0.4mmのドリルで穴を
開けておきました。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/10)
写真は神戸寄りパンタ周辺。
穴開けは1両当たり57か所になります。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/13)
配管渡り板をモニタルーフに半田付けします。 |
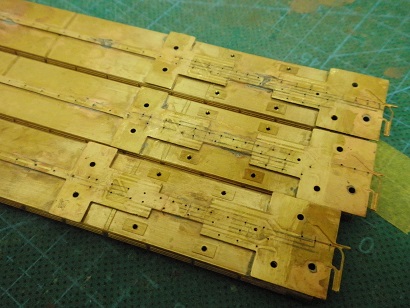 |
・配管渡り板組立(2024/9/13)
この状態で、配管止め穴をΦ0.4mmのドリルでさらって、
モニタルーフと貫通させます。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/13)
この状態で、配管止め穴をΦ0.4mmのドリルでさらって、
モニタルーフと貫通させます。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/14)
主配管はΦ0.4mm、その他はΦ0.3mmの真鍮線で
再現します。
Φ0.3mmはΦ0.2mm位の方が良かった気がします。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/14)
まずは1台分、配管を取付完了。
裏面から。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/14)
配管止めは市販のパーツは使用せず、線材をほぐした
ものを使用して割ピンの応用で取り付けています。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/14)
屋根上から全景。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/14)
写真は大阪寄りパンタ台周辺。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/14)
写真は大阪寄りパンタ台周辺。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/15)
3両分量産。.
|
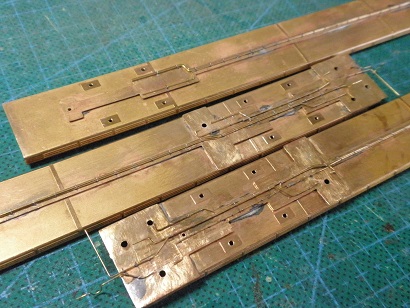 |
・配管渡り板組立(2024/9/15)
メーカー完成品とは差別化できたかと思います。 |
 |
・配管渡り板組立(2024/9/15)
ちょっと嬉しいので、配管渡り板を肴に一献。
2024/9/29 |
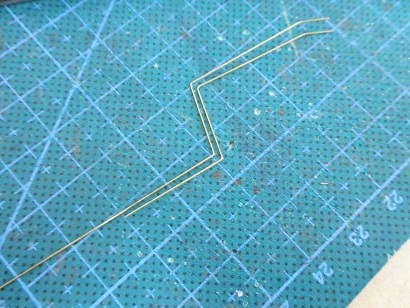 |
・配管取付(2024/9/16)
高圧配管などのパーツを取りつけていきます。
なお製品として空気配管は付いていないようですので、
Φ0.3mmの真鍮線で追加します。 |
 |
・配管取付(2024/9/16)
マステで仮止めして、半田を流します。 |
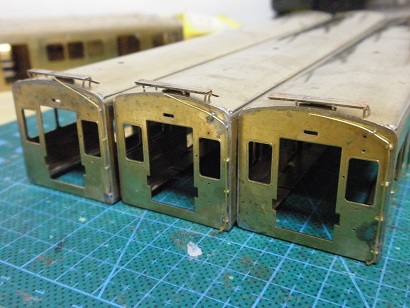 |
・配管取付(2024/9/16)
空気配管の取付完了。
屋根車端部のランボードは塗装後接着を考えていましたが、
パーツ足の強度が弱そうでしたので、取り付けることにしま
した。
既にランボードの足が折れている箇所があるので、後日
修正します。
|
 |
・配管取付(2024/9/16)
空気配管はこの後屋根に回し、車端ランボード上に
半田付けします。 |
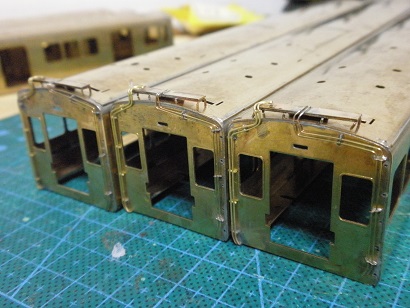 |
・配管取付(2024/9/16)
高圧配管、空気配管取付完了。 |
 |
・配管取付(2024/9/16)
空気配管の位置がやや下がり気味なので後日修正
します。
ひとまず取付けるものは取り付けたので、塗装に
備えます。
2024/10/6 |
 |
・シート組立(2024/9/24)
ちょっと塗装出来る機会が出来たので小物を。
シートを塗装して組立てます。
まずはシートの塗装を行い、端部の手摺を接着します。 |
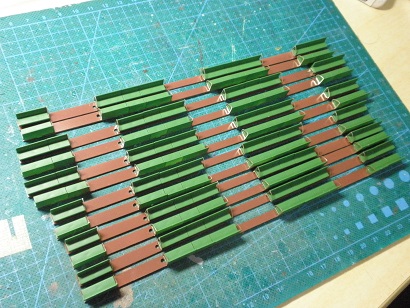 |
・シート組立(2024/9/25)
シート台座は床色を吹き付け、組立てたシートを接着
していきます。 |
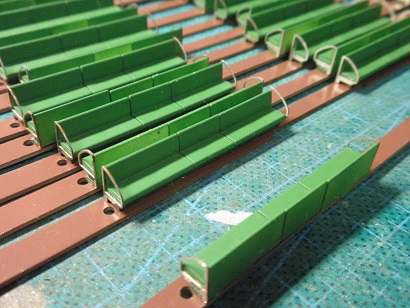 |
・シート組立(2024/9/25)
6両分組立完了。 |
 |
・室内照明関係組立(2024/10/1)
室内灯は定番の夕庵方式を採用しますが、カツミの車両
の場合、屋根上パーツ取付に関する出っ張りがあるので、
従来の基板厚(t=1.6mm)では高さ方向に干渉します。
よって薄手の基板を調達しました。 |
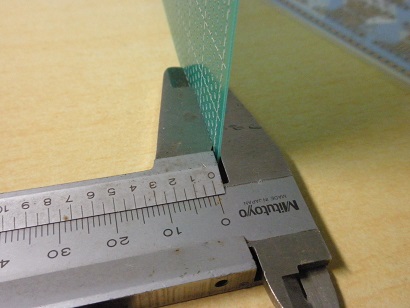 |
・室内照明関係組立(2024/10/1)
t=0.4mmのガラエポ基板。
ハサミでも着ることが出来るそうで、作業性は良さそうです。
今回回路構成を見直す予定です。
2024/10/13 |
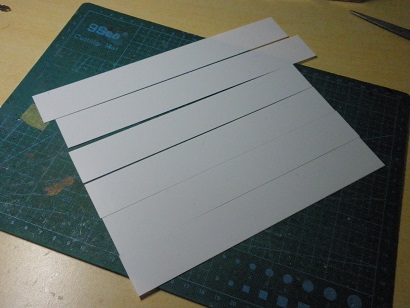 |
・室内照明関係組立(2024/10/2)
天井板はt=0.5mmのプラ板を使用します。 |
 |
・室内照明関係組立(2024/10/15)
基本配線は銅テープを使用した自作紙基板で行い、
線材を極力減らします。 |
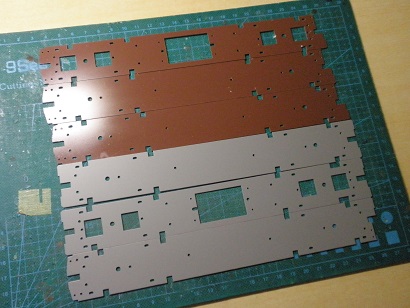 |
・床板塗装(2024/10/15)
塗装出来る機会があったので、床板を塗装。
室内はマッハNo.8:パレット貨車、床下側は手持ちの
マッハNo.23:明灰色を使用しています。
明灰色は少し明るめの様な気もしますが、当時は
グレーが現在より明るめだった記憶がありますので、
ねずみ1号の代用としました。 |
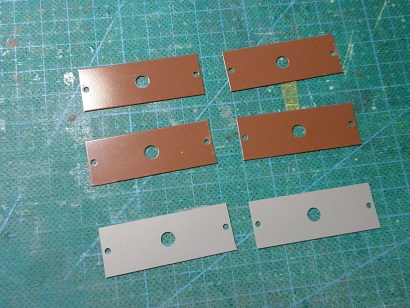 |
・床板塗装(2024/10/15)
MPギア部のカバーも同様です。 |
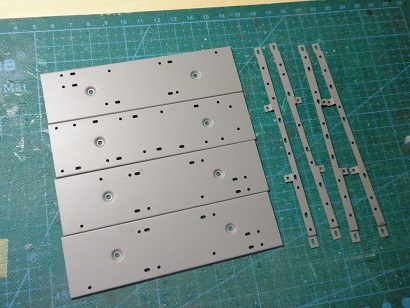 |
・床板塗装(2024/10/15)
床下機器の台座も同様です。
床下機器類まで手が回りませんでしたので、次回
塗装の機会が来るまで保留です。 |
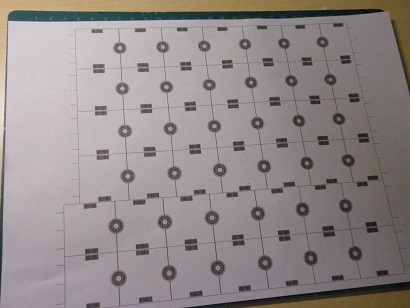 |
・室内照明関係組立(2024/10/15)
室内照明関係に戻ります。
まずは天井模様(夏仕様)から。
レイルロード社の聖書を参考に、おおよそのレイアウトを
決めて作図→印刷。 |
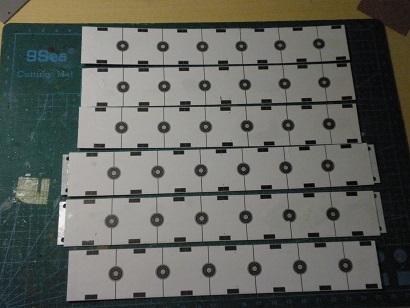 |
・室内照明関係組立(2024/10/18)
先に切り出したプラ板に貼り付けます。
中間車2両分の長さ方向の寸法が足りていない
ですね。 |
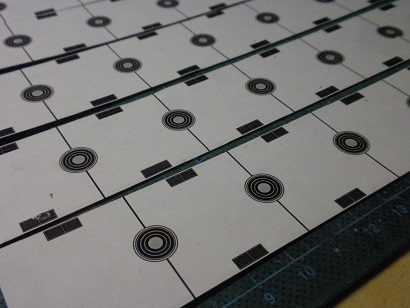 |
・室内照明関係組立(2024/10/18)
本当はファンデリアのところを抜きたいところですが、
雰囲気で充分かと印刷で済ませます。
そこまでする必要も無いのかなと。
ファンデリアカバーを作って、冬仕様にしようかとも
考えています。
2024/10/20 |
 |
・床下関係組立(2024/10/21)
塗装出来る機会があったので、台車や床下機器類を
塗装。
床板と同様マッハNo.23:明灰色を使用しています。 |
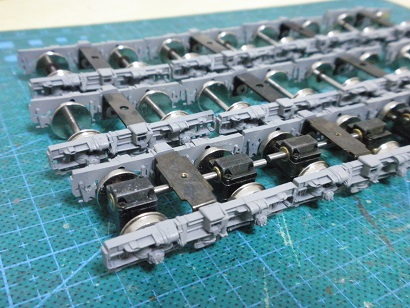 |
・床下関係組立(2024/10/21)
塗装して6両分組立ました。
動力は2両。MPを組込んでいます。 |
 |
・床下関係組立(2024/10/21)
床下機器類も塗装しています。
台座に取り付けていきます。 |
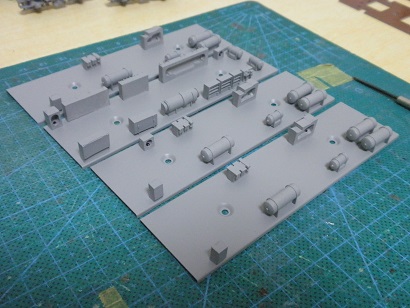 |
・床下関係組立(2024/10/22)
床下機器類を台座に取り付けました。
写真はモーターなし車用の4両分です。 |
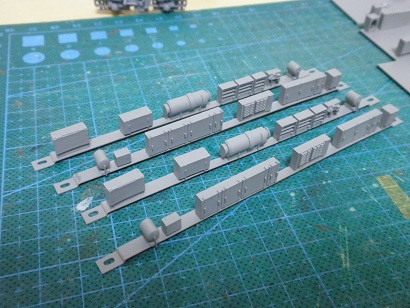 |
・床下関係組立(2024/10/22)
写真はモーター車用の2両分です。
組み上がった床下機器を、床板に取り付けていきます。
2024/10/27 |
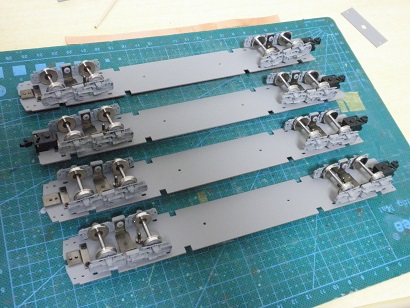 |
・床下関係組立(2024/10/23)
床板に台車を取り付けます。
まずはモーターなし車用4両。 |
 |
・床下関係組立(2024/10/23)
次はモーター車の2両分。
キットに付属頂いたEN-22を使用します。 |
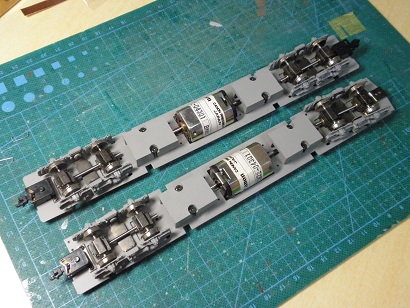 |
・床下関係組立(2024/10/23)
無事モータ取付完了。
実は付属のモーターは一般形で、指定品は短軸型。
当然長さが合わないので、モーター軸を切り落として
調整しています。 |
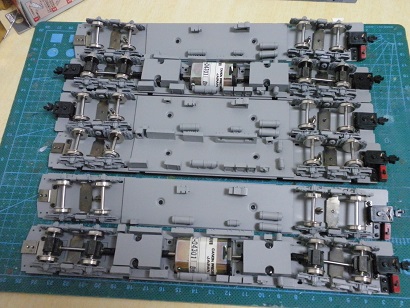 |
・床下関係組立(2024/10/26)
モーターなし4両も床下機器を実装。 |
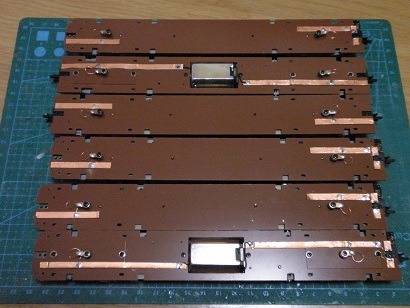 |
・床下関係組立(2024/10/26)
室内側俯瞰。
モータ用配線や照明用配線を取り付けています。
線材を少なくするため、銅テープを多用しました。 |
 |
・床下関係組立(2024/10/26)
床下類が組み上がったので、いつもの無負荷慣らし運転に
投入しました。
2024/11/3 |
 |
・仮組(2024/11/6)
ここで一旦仮組。
ある程度進んでくると、こういうことをやってみたく
なります。
結局進みが遅くなる訳ですが...。 |
 |
・仮組(2024/11/6)
オカさんのキットと比較して、前面がなんとなく「のっぺり」
した感じがします。
素材のせいか、方向幕や腰回りの標識灯有無による
ものでしょうか? |
 |
・仮組(2024/11/6)
側面より俯瞰。
特に干渉等の問題は無さそうです。 |
 |
・床下関係組立(2024/11/17)
ステップやジャンパ栓等のパーツを忘れていたので
塗装しておきました。 |
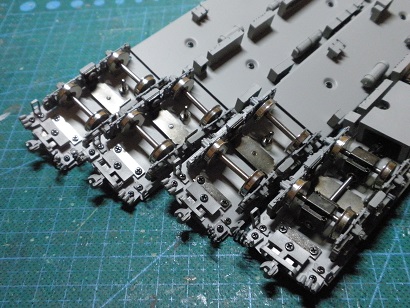 |
・床下関係組立(2024/11/19)
車体に取り付けます。
連結器はひとまず全車キット付属のダミー連結器を
取り付けておきました。 |
 |
・床下関係組立(2024/11/19)
再度車体と組み合わせると、なぜかホース付きジャンパ栓
の台座と干渉するようです。
スペーサを挟む等の対応を考えています。
2024/11/24 |
 |
・室内照明関係組立(2024/11/6)
製作日付は戻りますが、室内照明関係に戻ります。
先に作成した天井板に配線を行います。
配線は基本銅テープで行い、線材は極力短くなるように
しました。 |
 |
・室内照明関係組立(2024/11/6)
ヘッドライト、標識灯/尾灯はキット付属の電球を使用
しました。 |
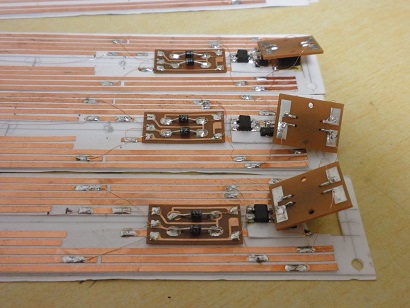 |
・室内照明関係組立(2024/11/6)
前照灯、標識灯/尾灯用ダイオードや、標識灯選択
スイッチ類もキット付属のパーツを使用しています。 |
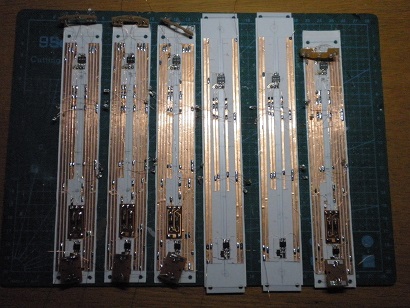 |
・室内照明関係組立(2024/11/23)
個人的都合で少し放置していましたが、製造再開です。 |
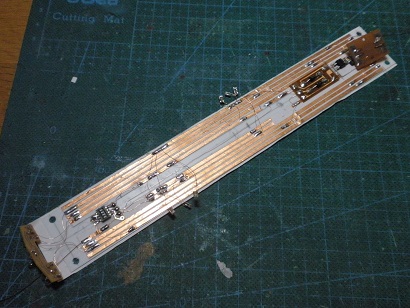 |
・室内照明関係組立(2024/11/23)
何を追加したのか写真では判りにくいと思いますが...。 |
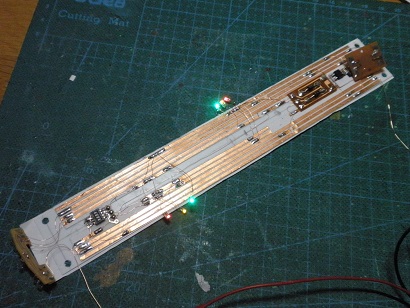 |
・室内照明関係組立(2024/11/23)
側面の種別表示器用のLEDを仕込みました。
写真左側のスイッチはその選択用です。
2024/12/1 |
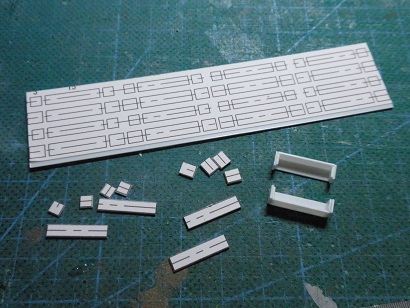 |
・室内照明関係組立(2024/11/25)
種別表示器用の遮光ケースを作成します。
t=0.5mmとt=0.2mmのプラ板を切出して、箱状に
組みます。 |
 |
・室内照明関係組立(2024/11/27)
仕切を付けて完成。
6両分12個となります。
|
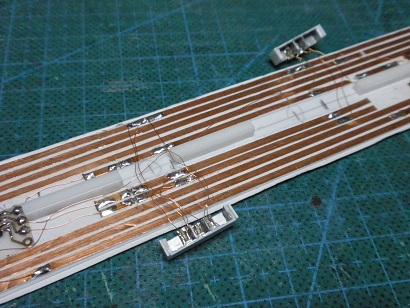 |
・室内照明関係組立(2024/11/28)
遮光性向上のため、内側に銀を色差しを行い
種別表示用のLEDを接着します。
|
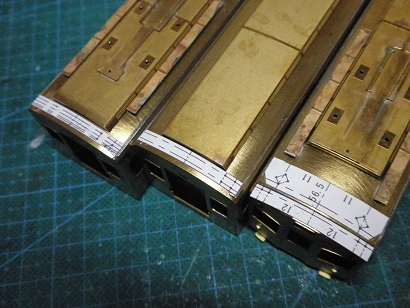 |
・屋根上手摺取付(2024/11/30)
屋根上の手摺類の取付を忘れていたので、後追い
実装。
穴開け位置決めのため、穴寸法をシール紙の印刷して
車体に貼り付けています。 |
 |
・屋根上手摺取付(2024/11/30)
穴開け完了。 |
 |
・屋根上手摺取付(2024/12/6)
Φ0.3mmの真鍮線を瞬着で固定しました。 |
 |
・屋根上パーツ塗装(2024/12/1)
日付は逆戻りしますが、屋根上パーツ類の塗装を済ませ
組立てます。 |
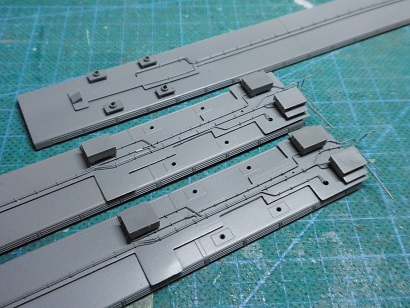 |
・屋根上パーツ塗装(2024/12/1)
パーツ類実装。
パンタ撤去側のパンタ台は、穴をふさぐ加工が必要なので
後日取り付けます。
2024/12/8 |
 |
・車体塗装(2024/12/20)
年末年始にマルーン塗装をできれば...と思い、
下地塗装に入ります。 |
 |
・車体塗装(2024/12/20)
酸洗い→クレンザー洗い→中性洗剤洗いで車体の
輝きを取り戻します。 |
 |
・車体塗装(2024/12/21)
洗浄後、塗装前にステップ類を接着します。
過去の経験上、作業中に曲げたり、折れたり、外れたり
することが多いので、塗装直前で接着することにしています。
前面はキット付属のステップを使用しています。 |
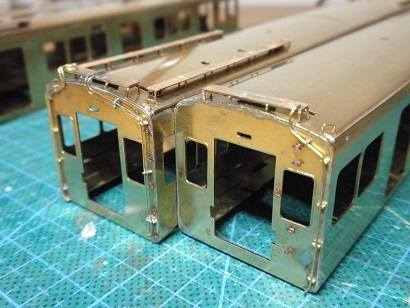 |
・車体塗装(2024/12/21)
妻面側はマッハの差し込みステップを使用しています。 |
 |
・車体塗装(2024/12/21)
まずは下地にミッチャクロンを吹きました。
今日はここまで。
室内色から吹いていきます。
2024/12/22 |
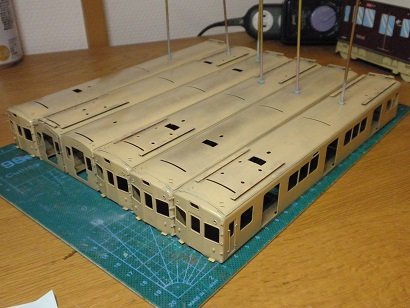 |
・車体塗装(2024/12/23)
塗装はまず室内色から。
吹込みよる表面のざらつきを押さえるため、表側も
同色を吹いています。 |
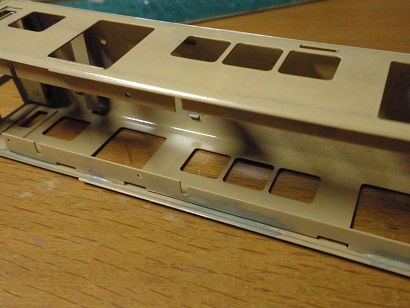 |
・車体塗装(2024/12/23)
どちらかというと室内側は念入りに吹いています。 |
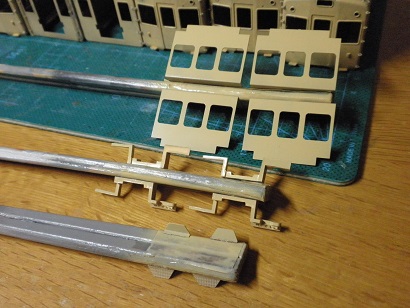 |
・車体塗装(2024/12/23)
仕切り板や、運転台も同色に塗装しておきます。 |
 |
・車体塗装(2024/12/28)
次は車体の下地塗装です。
室内をマスキングし、マッハのNo.4:赤13号を吹いて
います。 |
 |
・車体塗装(2024/12/28)
この段階から表面が平滑になる様に、また埃が付か
ない様に、注意して塗装していきます。 |
 |
・車体塗装(2024/12/31)
次にマルーン塗装になります。
昭和45年頃のマルーンはどうだったか記憶が怪しい
のですが、イメージでマッハNo.59B:阪急マルーン(新)を
使用しました。 |
 |
・車体塗装(2024/12/31)
薄めに溶かした塗料を、10回ほど塗り重ねました。
ただ、1両。
柚子肌が酷く、リワークが不可でしたので、潔く
シンナープールにドボン。
再塗装しました。
|
 |
・車体塗装(2024/12/31)
塗装後、食器乾燥機で乾燥させます。 |
 |
・車体塗装(2024/12/31)
車体マルーン塗装完了。 |
 |
・車体塗装(2024/12/31)
車体マルーン塗装完了。 |
 |
・車体塗装(2024/12/31)
昭和45年頃は、そんなにつやつやでは無かった
イメージもあり、光沢はやや抑えめです。
今年は珍しく、年内に塗装が終わり、正月三が日から
寒空の下で塗装することがなさそうです。
2025/1/5 |
 |
・車体塗装(2025/1/2)
新年は客用ドアの窓枠とドアレール類の磨き出し。
6両といえど新年早々の修行です。 |
 |
・車体塗装(2025/1/2)
まずまずでしょうか。
失敗(削りすぎ)は1か所。
リワークしておきます |
 |
・車体塗装(2025/1/2)
塗料の削りカスなどが残りますので、エアーで吹き
飛ばして綺麗にしておきます。 |
 |
・車体塗装(2025/1/3)
正月三が日は...と思いつつ、屋根の塗装です。
マスキングを施し、ガイアのNo.1005:ねずみ色1号を
吹いています。 |
 |
・車体塗装(2025/1/5)
屋根グレー塗装後は前面と妻面のサッシに銀を
差します。
|
 |
・車体塗装(2025/1/3)
目が悪くなってきた為か、色入れが苦手な作業に
なりました。
写真は前面。
この点はパーツ貼付け方法のオカさん方式が個人的には
作りやすいです。
|
 |
・車体塗装(2025/1/5)
写真は写真は妻面側。
|
 |
・車体組立(2025/1/5)
前面用パーツを準備します。
写真は幌枠と前照灯。 |
 |
・車体組立(2025/1/8)
窓セルを切出します。
今回室内側にデコラ模様シート貼付けを予定している
ため、出来るだけ薄くしたいと思い、製品パーツでなく
透明プラ板(t=0.2mm)を使用しました。 |
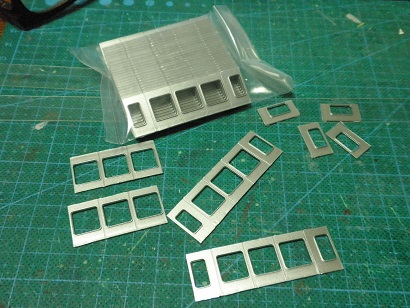 |
・車体組立(2025/1/8)
アルミサッシは、プラ製系パーツを車体裏側から貼付ける
構成です。
3連、2連と必要数を切出します。 |
 |
・車体組立(2025/1/8)
切出し完了。
種別表示器の周辺はあらかじ欠き取りを入れています。
このパーツに先に切り出した透明プラ板を貼付けて
いきます。 |
 |
・車体組立(2025/1/11)
客窓を貼り付けてみました(上)。
これで一気に阪急電車っぽくなります。
「阪急電車は窓枠で出来ている」と言っても過言ではないと
個人的に思っています。 |
 |
・車体組立(2025/1/11)
6両分窓セル貼付完了。 |
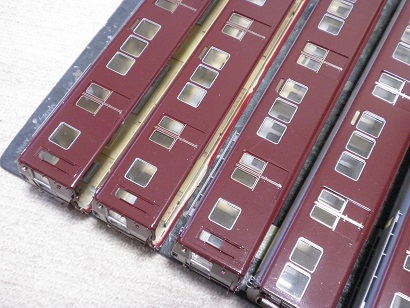 |
・車体組立(2025/1/11)
窓枠表現は、オカさんの窓枠パーツに比較すると、
どうしても劣ってしまいますが、その組立性と見栄えは
充分では無いかと思います。
2025/1/12 |
 |
・車体組立(2025/1/12)
前面幌枠とドアノブを取付けました。 |
 |
・車体組立(2025/1/12)
前面幌枠とドアノブ、種別表示灯のパーツを取付けました。
これで一気に阪急らしくなりました。
「阪急電車は幌枠で出来ている」と言っても過言ではないと
個人的に思っています。 |
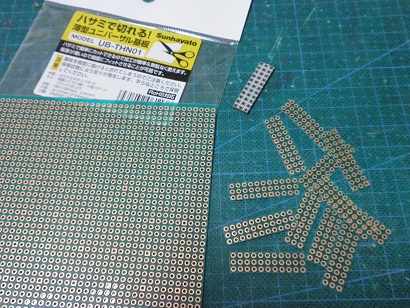 |
・車体組立(2025/1/12)
室内灯ユニットの室内灯用LED基板を製作します。
今回、レイアウトの関係から高さ方向の寸法を抑える
必要があり、t=0.4mmのガラエポ基板を採用しました。
ハサミで切断できることもあり、加工性が向上します。 |
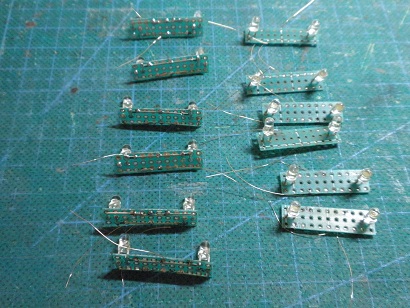 |
・車体組立(2025/1/13)
いつも通りΦ3mmの砲弾型LEDを2個/基板で実装
します。
今回整流用ダイオードを天井板側に実装し1個化とした
ため、この基板には実装していません。 |
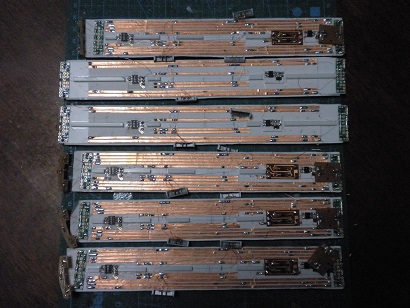 |
・車体組立(2025/1/14)
室内灯用LED基板を天井板に取付け、天井板に配置した
該当電極の銅テープに接続します。 |
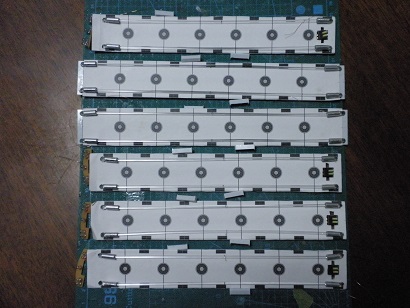 |
・車体組立(2025/1/14)
夕庵式ということで、室内灯用LED基板間に蛍光灯を模した
透明プラ棒を通します。
透明プラ棒を両側から照らして、光らせる構成です。 |
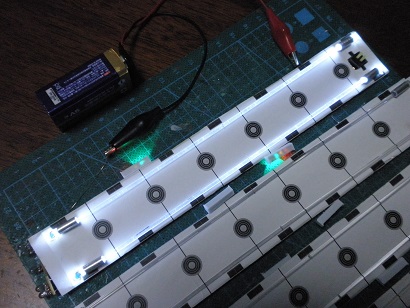 |
・車体組立(2025/1/14)
室内灯ユニットの試験点灯。
室内灯は問題なさそうです。
これから仕上げに入っていきます。
2025-1/19
|
 |
・車体組立(2025/1/15)
側面の種別表示器用に「特急|急行|準急」表示ボードを
作成します。
「特急|急行|準急」の表示はJWCADで作図後、
MDプリンターにデカール印刷し、透明プラ板に貼付けて
います。 |
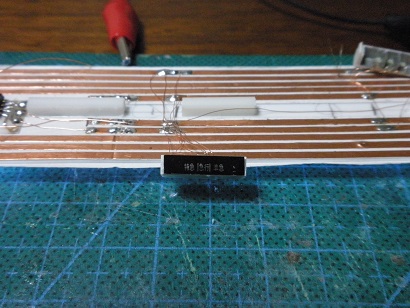 |
・車体組立(2025/1/15)
種別表示器用の遮光ケースに表示ボードを貼付ます。 |
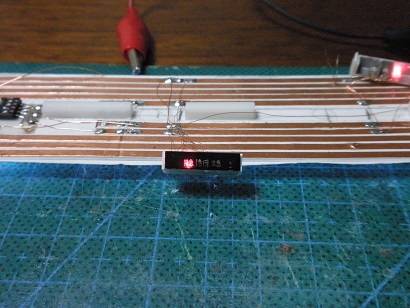 |
・車体組立(2025/1/15)
試験点灯「特急」。 |
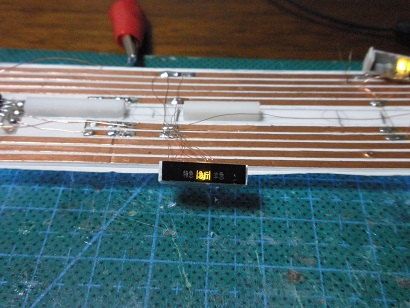 |
・車体組立(2025/1/15)
試験点灯「急行」。 |
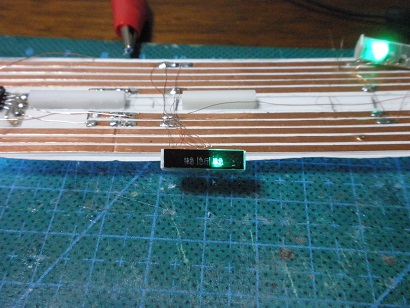 |
・車体組立(2025/1/15)
試験点灯「準急」。 |
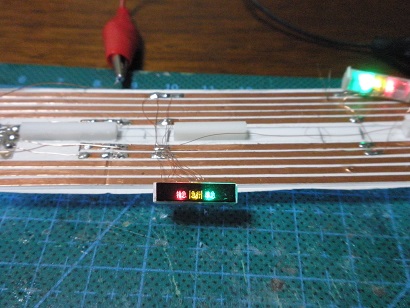 |
・車体組立(2025/1/15)
実車ではありえない「全点灯」。
実現して見たかった種別表示器点灯化。
何とかなりそうです。
2025/1/26
|
 |
・車体組立(2025/1/25)
運転台パーツのメーター部に色差ししておきます。
|
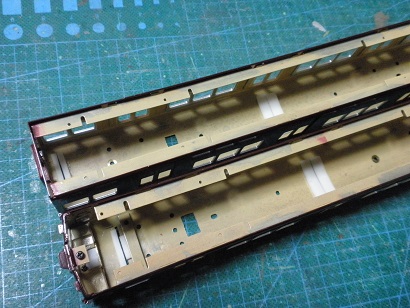 |
・車体組立(2025/1/29)
種別表示を切り換えるためのスイッチは天井から
アクセスする事を考えています。
よってモニタ-ルーフの取り外しができるようにします。
モニタルーフの固定方法として、モニタルーフの足を
ゴム素材で挟みこむようにしてみます。
消しゴムを薄くスライスし、天井裏に貼り付けておきます。
|
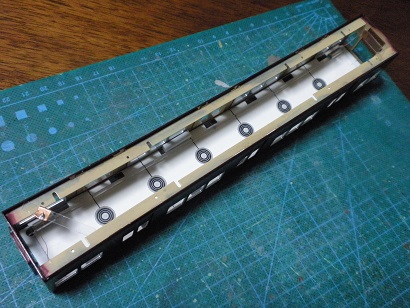 |
・車体組立(2025/1/29)
室内灯ユニットを車体に組み込みます。 |
 |
・車体組立(2025/1/29)
天井側からの俯瞰。
開口部に無事スイッチがが顔を出しました。
スイッチはこちらから操作します。
2025/2/2
|
 |
・車体組立(2025/2/4)
照明関係の点灯確認。
前照灯、種別表示灯は無事点灯。
|
 |
・車体組立(2025/2/4)
照明関係の点灯確認。
尾灯も無事点灯。
|
 |
・車体組立(2025/2/4)
照明関係の点灯確認。
室内灯も無事点灯。
|
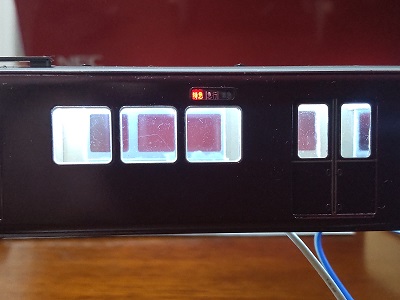 |
・車体組立(2025/2/4)
問題の種別表示。
まずは「特急」。 |
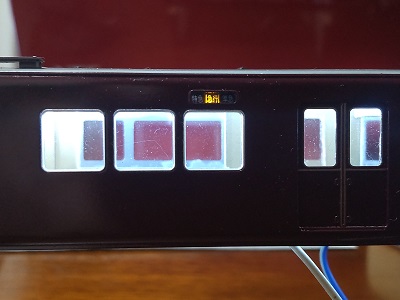 |
・車体組立(2025/2/4)
「|急行|」。 |
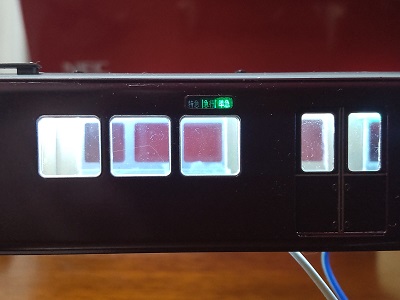 |
・車体組立(2025/2/4)
「準急」。
もう少し光量を落とした方が良かったかもしれません。
|
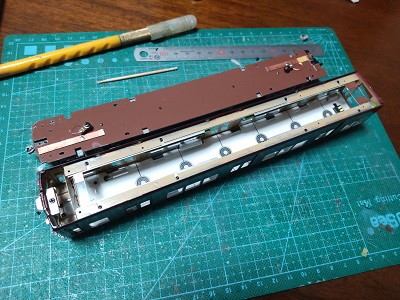 |
・車体組立(2025/2/6)
先に組立てたシートを実装。 |
 |
・車体組立(2025/2/6)
内装にデコラシートを貼り付ける予定ですが、まずは
仮落成を目指し組立を進めます。
キット付属のシートは端部の手すりパーツが付属して
いるので、真鍮線曲げて接着等の作業が不要で
助かります。
2025/2/9 |
 |
・車体組立(2025/2/9)
車体と床板を組合わせてみました。 |
 |
・車体組立(2025/2/9)
前面から俯瞰。
だいぶと阪急らしくなってきました。 |
 |
・車体組立(2025/2/9)
Mc車を側面から俯瞰。 |
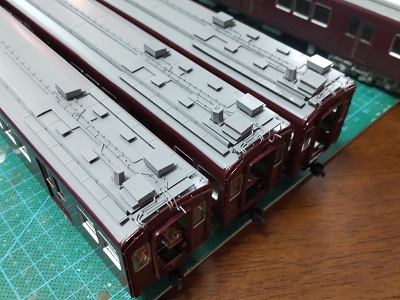 |
・車体組立(2025/2/9)
大阪寄りパンタ台周辺。 |
 |
・車体組立(2025/2/9)
神戸寄りパンタ台周辺。 |
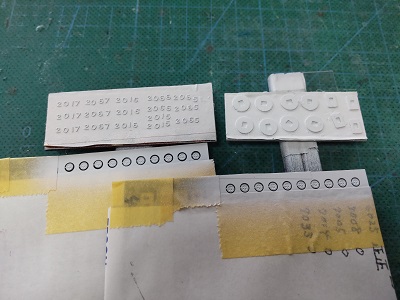 |
・車体組立(2025/2/9)
車番貼付けに向け、マッハの車番と社章パーツの白を
吹いておきます。 |
 |
・車体組立(2025/2/9)
入手したパンタ(PT-43)はグレータイプでしたので、同時に
銀を吹いておきます。 |
 |
・車体組立(2025/2/13)
車番および社章を貼付け完了。 |
 |
・車体組立(2025/2/13)
前面より俯瞰。
この顔を見、やはり「阪急は車番で出来ている」と思って
しまいます。 |
 |
・車体組立(2025/2/13)
再びMc車を側面から俯瞰。 |
 |
・車体組立(2025/2/18)
ワイパー実装。
キット付属のパーツを実装しようとしたところ、ストローク
長が短く却下。
エコーのパーツも試しましたが、やはり短いです。
最終的にホビーメイトさんの7000系キット付属の余った
ワイパーを採用しました。 |
 |
・車体組立(2025/2/18)
先に銀塗装したパンタを取り付けます。
これにて、取り付けるものは取り付けました。 |
 |
・車体組立(2025/2/18)
パンタ上昇。
何となく、ちょっとデカい気がします。 |
 |
・車体組立(2025/2/18)
再びMc車を側面から俯瞰。 |
 |
・車体組立(2025/2/18)
これにて6両落成です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
2025/3/2 |
 |

・車体組立(2025/2/18)
遅ればせながら、看板の作成です。
キット付属のパーツを白塗装し、キット付属のシールを
貼り付けています。
種別表示を切換えできるようにしましたので、特急、急行
準急、普通の全種類を用意しました。
準急の設定は、池田-大阪ではなく、宝塚−大阪か
箕面−大阪にして欲しいところです。 |
 |
先頭車:2016(右)と2065(左)
・基本は須磨浦公園の青看板+ブレーブス坊やの
2枚看板としています。
中間に挟まれる2016は、撮影用に急行を取付けて
います。
|
 |
先頭車:2017(右)と2067(左)
・基本は須磨浦公園の青看板+ブレーブス坊やの
2枚看板としています。
中間に挟まれる2067は、撮影用に急行を取付けて
います。
2025/3/30
|